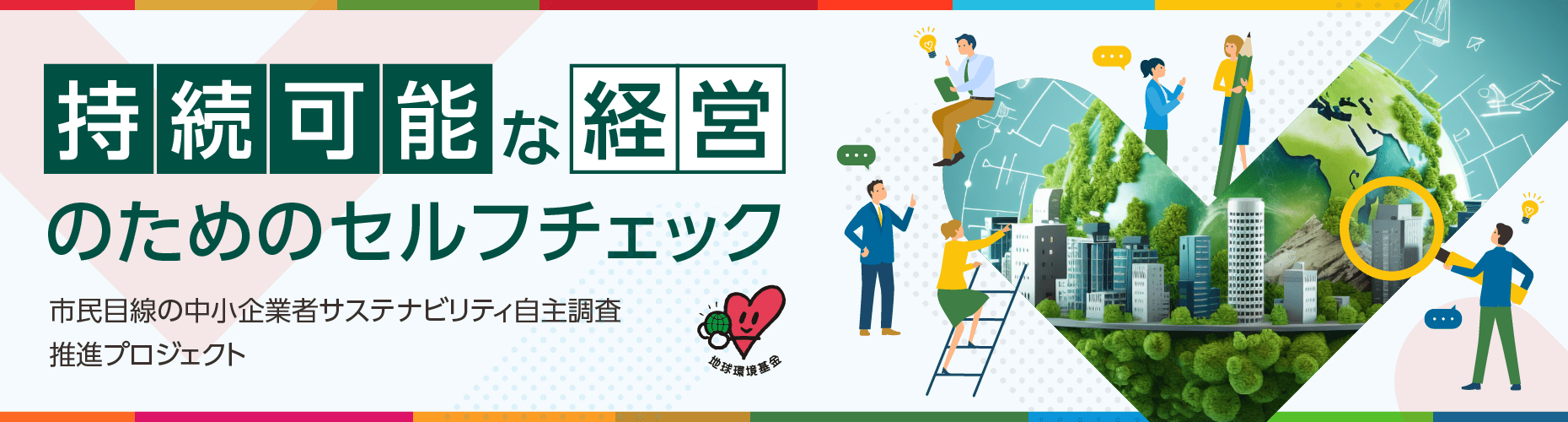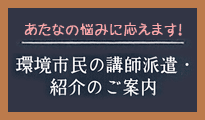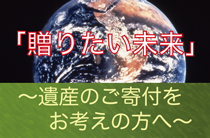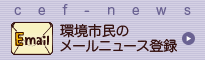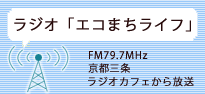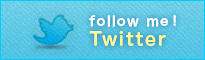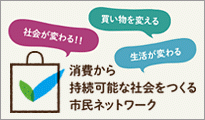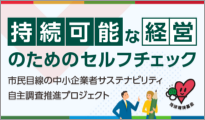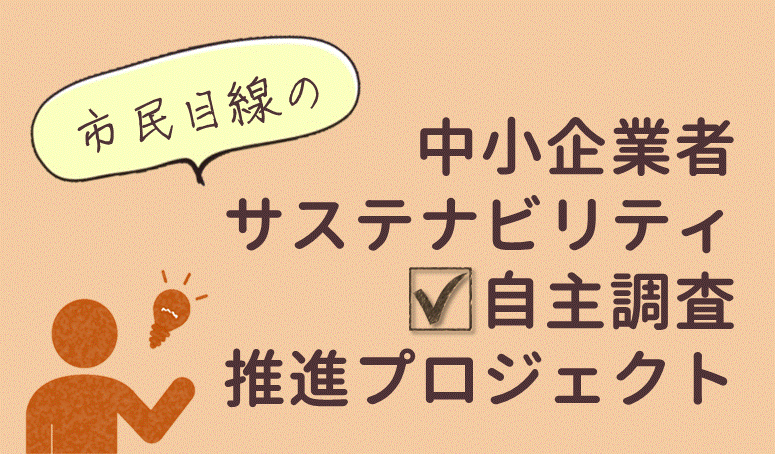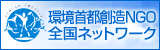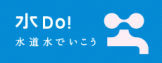21世紀、地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに
持続可能な経営のためのセルフチェック
セルフチェックの目的
昨今、気候変動や生物多様性などの環境問題、SDGs の諸課題の解決に繋がる取り組みが企業活動の中でも求められています。中でも、地域の持続可能性を高めていくために重要な存在である中小企業者の CSR 活動が向上し、その地域の住民や消費者が中小企業者の取り組み情報をわかりやすく得られるようになることは、地域経済にとっても有用といえます。
また、企業経営の持続可能性という点を見ても、まずは自社の状態や、立ち位置を認識することは重要です。そこで、企業や事業者がサステナビリティ自主調査票を用いて自己チェックができる仕組みを、地元の経済団体や活動団体等とのパートナーシップにより構築することを目的として、本プロジェクトは始まりました。
本プロジェクトでは、持続可能な社会づくりや SDGs の取り組みに資することを目的とし、大企業を対象として 5 年にわたり消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク(事務局:環境市民)で実施してきた、市民目線での CSR・サステナビリティ調査「企業のエシカル通信簿」を活用し、「持続可能な経営のためのセルフチェック(中小企業者サステナビリティ自主調査票)」として実施します。
実施にあたっては、地域の経済団体とのパートナーシップを重視し、地域の状況に応じた中小企業者の環境・サステナビリティの取り組みを高めるサポートをしていきます。
セルフチェック調査票について
調査票の項目は、以下の通りです。
- サステナビリティ体制
- 消費者保護・支援
- 人権・労働
- 社会・社会貢献
- 平和・非暴力
- アニマルウェルフェア
- 環境(A ガバナンス、B 気候変動、C ごみ削減、D 生物多様性、E 化学物質、F 水))
この調査票をもとに、自己チェックを行っていただきます。
調査票の回答方法やポイントについては、以下の動画で解説をしています。
地域の導入事例
2022年度~ 長野県にて実施(実施状況についてはこちら)
2022年度~ 秋田県にて実施
2023年度~ 滋賀県にて実施(実施状況についてはこちら)
研修・動画素材
プロジェクト説明動画~企業様が調査票に取り組む意義~
事前研修動画はこちら(パスワードが必要です)
事後研修動画~各分野別の回答ポイント
動画ページはこちら(パスワードが必要です)
イベント情報
2024年2月に報告交流会を開催します

中小企業のみなさんが、まずは自分たちの状態を知ることから始め、自社だけでなく地域を持続可能にしていくためのサステナブル度を測るセルフチェックに挑戦しています。
今年度は、長野県、秋田県に続いて滋賀や京都でも取り組みがはじまりました。
その活動を広く知ってもらおうと交流報告会を行います。
中小企業のみなさんだけでなく、頑張っている企業を応援したい方、就活中の学生のみなさん、ぜひ熱い思いを持つ中小企業の話を聞きにきてください。
●とき : 2 月 27 日(火)13:30〜
●ところ : 京都経済センター4 階 B *オンライン参加も可
(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地 地下鉄四条駅北改札出てすぐ)
●対象:どなたでも参加できます
●無料
●申し込み : 下記のフォーム、または QR コードからお願いします。
(申込締切 : 2024 年 2 月 20 日(火)必着)
https://forms.gle/taum7k7dqE7J5Jnj8
フォームが使えない場合は、メール:life@kankyoshiimn.org、電話、FAX で、お名前、所属・連絡先に加え、オンライン、現地参加のどちらを希望されるかもお知らせください。チラシPDFはこちらから↓
過去のイベント・取組み
過去のイベントはこちらからご覧いただけます。
このサイトについて
このページは、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて製作しました。