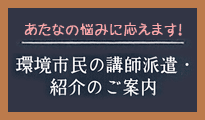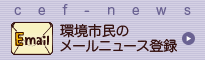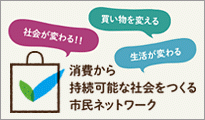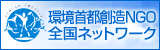21世紀、地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに
第3回動物たちの瞳
文/代表理事 すぎ本 育生
「寒い!」ケニアの朝、初めの感覚はこれだった。サファリ*に出る前、まだ夜が開け切れぬレストランではコーヒー、紅茶が供される。席の後ろには、かがり火のように炭が燃され寒さが和らげられている。ナイロビから人類誕生の地でもある大地溝帯を越えて西に位置するサバンナ、マサイマラは、標高2000メートルの高原地帯にある。アフリカの動物達が棲む草原は、熱帯にあるという先入観は打ち砕かれる。日中の日差しはきついが気温は20℃を超える程度、夜ともなるとホテルのベッドには湯たんぽが入れられているぐらいだ。
サファリカーに乗って動物達に会いに行く。ここは生き物達の世界、人間は歩くことはできない。夜が明けてきた。なだらかな曲線を描く草原と疎林、そして空が真紅に染まっていく。張り詰めた冷気の中、たおやかな時が刻まれる。
マサイマラはマサイ族の住む草原という意味、ケニアの中でも最も哺乳動物が多く棲息していると言われている。現在は動物保護区になっている。子供のころテレビで見て憧れた、でも自分の目では見ることは難しいと思っていた「野生の王国」にいま入っている。サファリカーから動物を捜す。最も多く現れるのはシマウマの群れ、その鮮やかなゼブラ模様は美しい。
遠くから私たちでも見つけられるのはキリンぐらい。ゾウのような大きな動物でも遠くから見つけることは難しい。キリンはとにかく高い、ほんとうに高い。動物園で見るのとはまるで違う高さを実感する。(キリンは数メートル首を上下するが、それでも貧血を起こさないしくみが身体の中にあるという。)
 ゾウはメスと子ゾウたちで群れをつくる。大きなゾウが外側に立ち、子ゾウたちを中に入れて守りながら草を食む。母ゾウが歩き出すと、子ゾウはあわててトコトコとついていく。追いつくと母の脚にぴったりと寄り添う。
ゾウはメスと子ゾウたちで群れをつくる。大きなゾウが外側に立ち、子ゾウたちを中に入れて守りながら草を食む。母ゾウが歩き出すと、子ゾウはあわててトコトコとついていく。追いつくと母の脚にぴったりと寄り添う。
サファリカーのドライバー兼案内役はマサイ族のパトリック。「ライオンがいる」と言い双眼鏡を使って確認する。でも私たちが双眼鏡で見ても全くみつけることができない。視力も動物の気配を感じる力も全く違う。1~2分ほどクルマで走るとライオンが現れた。群れで食事中であった。獲物はシマウマ、残酷さはほとんど感じない。それはライオンが生きていくために必要なことだからか。そうではないのに多くの同属や生き物を大量に殺すのは人間だけだろう。どちらが「ケダモノ」かははっきりとしている。子ライオンが食べるのを母ライオンがじっと見守っている。
その時、ライオンの耳の裏側が黒色であることをはじめて知った。動物園やテレビ番組などで見ていたはずなのに記憶になかった。見る動物すべて動物園とは違う、ここは彼らが本来生きている大地なのだ。眼が澄んで輝いている、身体が汚れていず、無駄な肉はついていない。精悍という文字が頭に浮かんでくる。動物園や水族館は、多くの生き物達がこの地球に生きていることを知ることができる貴重な施設であろう。ただ、本来の生き物達の表情や姿を見られるとは限らない。
 「チーターを捜しにいこう」パトリックがタンザニアとの国境近くまでクルマを走らせていく。途中、尻尾をたてて走るイボイノシシ、樹上に巣を作り大きな翼を広げて飛翔するハゲワシ、地上最も早く走る鳥ダチョウ、鼻の頭がハート模様ウォーターバック、百頭を超える昼寝のカバの群れなど多くの動物達に出会いながらサファリは続く。パトリックがチーターを見つけた。例によって私たちには見えない。近づいていってやっとわかる。草原の小さな岩に3頭のチーターがいた。母と2頭の子供だとパトリックは言うが、私たちには区別がつかない。遠巻きに望遠レンズで写真を撮り、双眼鏡を覗く。斑点模様が見事なまでに美しい。遠くからでもその身体がしなやかなことが感じられる。
「チーターを捜しにいこう」パトリックがタンザニアとの国境近くまでクルマを走らせていく。途中、尻尾をたてて走るイボイノシシ、樹上に巣を作り大きな翼を広げて飛翔するハゲワシ、地上最も早く走る鳥ダチョウ、鼻の頭がハート模様ウォーターバック、百頭を超える昼寝のカバの群れなど多くの動物達に出会いながらサファリは続く。パトリックがチーターを見つけた。例によって私たちには見えない。近づいていってやっとわかる。草原の小さな岩に3頭のチーターがいた。母と2頭の子供だとパトリックは言うが、私たちには区別がつかない。遠巻きに望遠レンズで写真を撮り、双眼鏡を覗く。斑点模様が見事なまでに美しい。遠くからでもその身体がしなやかなことが感じられる。
生き物の美しさと生きていることの大切さと切なさ、そしてこの星が決して人間が自由にしていいものではないことが、心に染み込んできた。
※サファリ・・スワヒリ語で旅を意味する。どのような移動手段を使っても、また短距離でもサファリという
写真はいずれも すぎ本育生が撮影