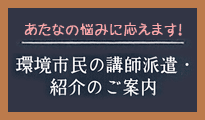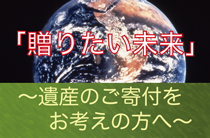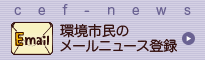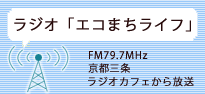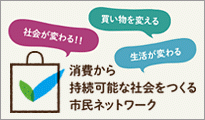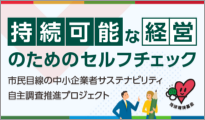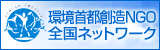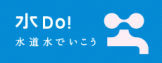21世紀、地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに
「ずっと住みたいまち」を交通でつくろう
カテゴリ: 電子かわら版コラム | 更新日:
このコーナーでは、ウェブやメールマガジンの企画運営を行っている「電子かわら版チーム」メンバーのコラムを紹介しています。一緒に企画運営をしたいボランティアも随時募集中です。関心のある方は京都事務局まで。

講演をお願いした先生から現地を視察したいと要望を受け、半日かけてバスでまちをめぐり、ご案内してきました。
普段は自転車ばかりなので、初めてバスに乗ってみた私の感想は「意外と便利」です。遠回りするのではないかとか、バス停がわからないのでは、という心配は杞憂でした。バス停に駐輪場が整備されていたことにも感心しました。
一方で料金の高さには驚かされました。これでは子どもをバスで通学させずに親がマイカーで送迎するという気持ちもわかります。
自動車の普及に押されてバス路線は全国で衰退していきました。
コロナ禍でさらに減った公共交通の利用者は今も戻りきらず、
そこに運転手不足も重なって、便数が減るなどサービスは低下しています。
私の住んでいる滋賀県では、鉄道やバスの整備に関する県政への不満度が
10年以上ナンバー1の記録を更新し続けています。
人々の暮らしを支える地域交通がどうあるべきか、
滋賀県では2023年度から
県民の意見を集め対話を試みるワークショップやフォーラムを重ねてきました。
昨年度はそのワークショップで意見を引き出すお手伝いをさせていただきました。
その中で、交通は都市計画と一緒に考えないとうまくいかないのにそうはなっていないこと、
自分たちが住んでいる地域に対して住民の間に
どうしていきたいという共通のビジョンがないことが、大きな問題であると感じてきました。
そこで、交通まちづくりに取り組む仲間に相談して、
足りない情報を補い、交通まちづくりを自らの問題として感じてもらうための
連続フォーラムを企画することになりました。
8月からフィールドワークを交えて、様々なテーマで地域交通を掘り下げていきます。
暮らしているまちが「ずっと住みたい」と思えるためには、
地域の交通手段はどんなふうであったらよいのでしょうか。
学校に通うには? 免許を返納したら? 誰かに頭を下げることなく、
自分の力で自分の行きたいところに行く選択肢が、誰にもちゃんとある。
そんなまちに住みたいと思いませんか。
移動の確保は、地方部なら全国どこにでも共通する課題です。
魅力的なまちをつくった先進地の事例を聞いたり、暮らしと交通の現場に足を運んだりして、
住んでいるまちの未来を一緒に考えてみるのはいかがでしょうか。(げの字)
●まちと交通の未来づくりフォーラム
ずっと住みたいしあわせのまちを目指して
<今週のコラムニスト>
ペンネーム:げの字
環境市民の設立3年目からの会員で、かつて事務局スタッフとして広報や環境教育を担当。
現在は滋賀県内で自転車通勤やエコ交通の推進のため、日々スポーツバイクと公共交通で駆け回っている。