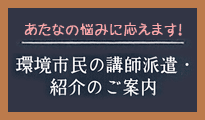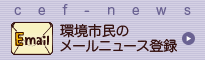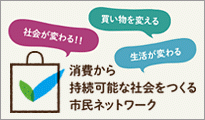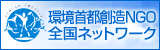21世紀、地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに
不可解な自己責任論―イラク人質事件をNGOの眼で検証する
環境市民「みどりのニュースレター2004年6月号(133号)」より
特定非営利活動法人 環境市民 理事会
今年4月8日、市民活動家の高遠菜穂子さん、今井規明さん、ジャーナリストの郡山総一郎さんら3人がイラク・ファルージャ近郊でイラク人武装グループに拘束され、一時生命が危ぶまれる事態に陥った。これに対し、多くの人が彼らを助けたい、殺されてなるものかと声をあげ、行動をとった。さらにはその後、ジャーナリストの安田純平さん、渡辺修孝さんも拘束され、拘束された日本人は5人となった。
幸いにして、武装グループおよびイラク人の多くが、彼らのイラク入りの目的を理解し、彼らは無事解放された。しかし、解放後の彼らに待っていたのは、「国の発した退避勧告を無視する者として自業自得」「自己責任を知らぬ無謀な行為」「救出に国が要した費用を支払わせるべき」などの言葉であり、その重さは、彼らを押しつぶさんばかりである。
この問題を看過することは、市民の良心に基づく自発的な活動を否定することになりかねないと思い、今回この問題を採り上げた。市民活動を実践する団体として、この問題に向き合い、意見を発信したい。
彼ら5人が危険を承知で、イラクの中でも特に危険な状況になっていたファルージャに近寄り、拘束されて以降、「自己責任」を問う論が出てきた。彼らのうち4人はもともとイラクで活動していた人たちである。彼らも、拘束という事態が自己の責任において発生したことは、よく理解していたはずである(彼らが活動できないほど危険な状況がどうして生まれたか、イラク戦争の目的や米軍の駐留政策などから考える必要があるが、ここではそこに入らずにおく)。
それでも声高に「自己責任論」が出てきたのは、彼らを拘束した武装グループから発せられた解放条件に「自衛隊撤退」があり、被害者家族や支援者たちがそれを国に強く要求したところからである。国の立場とすれば「人質をとられたから撤退する」と軽々に言えないのだろう。しかし、「自己責任論」が「国策と反する者」を封じる込めるため、個人の行動に規制をかける言葉として用いられているように感じた。人道支援では、国レベルでこそ、できることがある一方、行政では機動性が乏しく手の届かないことが多々ある。それは1995年の阪神淡路大震災によって明らかになったはずである。
拘束された人たちのイラク入りの目的や、これまでの活動が伝わると、多くの人が「危険をおかしてまで、イラクの人たちに尽くそうとする人たちを殺させてはいけない」と声をあげた。もし彼らがオイルマネーを目当てに一獲千金を求めた人たちなら、このような共感・共鳴は広がらなかっただろう。幾万もの人たちが、彼らの目的やこれまでの活動を知ったうえで、「同じ社会に生きる者の責任として、彼らを助けたい」と思った時、その思いを実現することは十分「国の責任」となり得たのではないだろうか。中には、この問題を「雪山遭難」と同質に論じるものまであったが、この例えは問題を見誤っていると言わざるを得ない。
そもそも「国」とは、個人がそれぞれの幸福の実現のため、権利の一部を国に預け、かつ義務を果たすことで成り立っている。国にはその付託に応える責任がある。今回耳にした「自己責任論」の中には、国の成り立ちそのものを見誤っているものもないだろうか。海外のメディアが奇異に感じているのもそこであり、「お上」といった発想まで見えてしまう。この考えの恐さは、個人または市民層の良心にもとづく自発的な動きを大きく制限しかねないことである。
ただし、楽観しているのは、一時高まった「自己責任論」に対して、反論が各所からあがっていることである。「自己責任論」を声高に叫んでいた者は、いずれその狭量を指弾される時がくるだろう。
今回拘束された5人のような人たちが、私たちと同じ社会に居たことを誇りに思いたい。
(文/環境市民事務局 堀 孝弘)