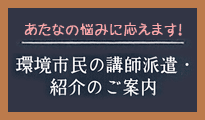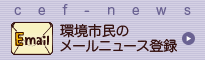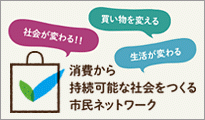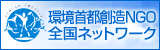21世紀、地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに
第9回 涸沢の秋
文/代表理事 すぎ本 育生
京都のイロハカエデの紅葉とは、全く異なる錦秋が広がっていた。真紅、朱色、黄金色、黄緑、緑に染まった潅木がパッチワークを描いて曲線的に大きく広がっている。ナナカマドの赤、ダケカンバの黄、ハイマツの緑が織り成す色鮮やかな世界。そこに岩肌の茶と灰、澄み切った空の蒼が加わる。そして時には初雪の純白も。三段染め、五段染め、さらには七段染めとも表現される。日本の山岳紅葉の代名詞ともなっている涸沢(からさわ)の9月末から10月初めの風景だ。穢れのない空気を身体一杯に吸い込み、この自然に溶け込む。
涸沢は北アルプス穂高連峰の懐、海抜2400メートル〜3000メートル付近にかけて丸く広がる谷である。日本にもかつて氷河があった何よりの証となるU字谷である。その上部は森林限界を完全に超えており、岩肌と可憐な高山植物の世界であるが、下部には背の低い木々が生え、下界よりも一足も二足も早い秋を迎える。
涸沢に入るには多くの日帰り観光客が押し寄せる上高地から歩き出す。ただ上高地はマイカーの乗り入れを禁止しているので交通渋滞による環境被害は蒙っていない。またバスやタクシーも上高地までしか入れない。上高地の河童橋から眺める岳沢、梓川の風景は見事だが、朝一番か夕刻に行かないと静けさは求められない。上高地は五千尺と呼ばれる海抜1500メートルにある。
ここからカラマツ、イチイ、コナシ、クマザサなどで形作られた森の道を梓川の左岸沿いに上流へ向かう。標高差はあまりなく、透き通った青と緑に変化する梓川の色を楽しむ。前穂高の前峰である明神岳が迫り、日盛りに河原の石が白く輝く。
1時間ほどで明神に着く。明神には穂高神社の奥社があり、深い静けさに囲まれた明神池がある。ここから先は観光客はもう来ない。ケショウヤナギが美しい梓川沿いにさらに1時間歩くと徳沢に着く。徳沢はかつて牛馬が放牧されていたため、森に囲まれ沢水が小川を作る草原になっていて何日でもテントを張っていたくなるキャンプ場だ。その徳沢からさらに1時間、横尾に着く。ここまでは登山する人間にとっては散策路。
梓川に架かる橋を渡り横尾谷に入っていく。道は幅が狭くなり、最初は苔むす森の中に入っていく。やがて河原に出るが左手の屏風岩が迫ってくる。1時間ほどで本谷橋に着き清冽な流れを渡る。ここからが「新人殺し」とも呼ばれたつづら折れの急坂が続く。テントなど山の道具が進歩し軽量化されたから昔ほど重くはないが、調理器具、食糧、水など20㎏ を超すザックが身体に重くのしかかる。速度を落とし、一歩ずつゆっくりと脚をすすめるのが疲れないコツだ。汗もポタポタと落ちてくるが気分は爽やかだ。半時間に一度の小休憩を入れながら1時間半ほど登ると眼の前が大きく開け、前穂、奥穂、北穂と続く穂高連峰が姿を現す。涸沢に到着だ。さらに半時間ほど色とりどりの潅木を縫うように傾斜が緩くなった道を涸沢の中心に進む。
涸沢には2件の山小屋があり、その間にキャンプ地が指定されている。日本アルプス内では生命の危険がない限り、指定されたキャンプ地以外ではテントは張れない。自然への影響を思うと当然のルールである。ここのキャンプ地は草原の徳沢とは違い、石に覆われている。平たい石が多いが眠るときは寝袋の下に二重にマットを敷く。それでも硬い。しかし、この自然を味わえるなら大したことではない。
10月 初めとは言え、夜になれば海抜2500メートルは冷える。寝袋の中でセーターを着ていても夜明け前は震える。寒さで起き出し、ウイスキーをたっぷりと入れた紅茶を飲むと身体が少し柔らかくなる。黎明の深い青に囲まれた影絵のような山々を眺めながら、夜明けを待つ。やがて空の青が変化し、光が差し込み始める。涸沢からみると穂高は西側になるので、陽を真横から浴びたように山肌が赤く染まる。日本の登山用語はドイツ語が多いが、この朝焼けもモルゲン・ロートと言われる。荘厳としか言い表しようのない。多くの人は自然の中で朝日を見ると、謙虚になれる。その気持ちを普段でも大切にしたいが、現代社会はあまりにも酷いことが多い。その社会を少しでも変えていくには、自然の力を時々もらいにいくことが必要なのかもしれない。
(みどりのニュースレター 2006年11月号 No.162掲載)